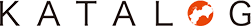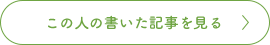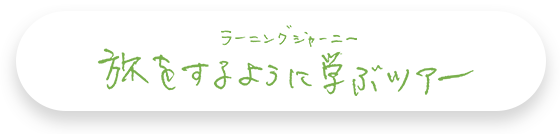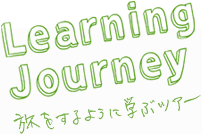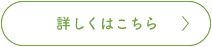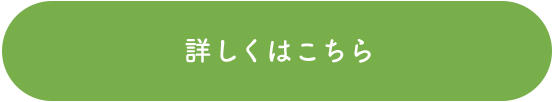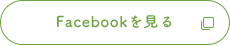はじめまして。
北海道浦幌町役場の須田です。
浦幌町役場ではゼロカーボンとDX推進に関する業務を担当し、私生活では自称:魚をさばく公務員として魚をふるまう「魚会」を開催する魚マニアです。
今回、「地方創生先進地地域滞在型研修」として、徳島市と神山町に滞在しました。3泊4日の濃密な滞在期間のなかで、特に印象に残った出来事を書かせていただきます。

Contents
はじめに(研修前の気持ち)
役場での担当業務は、行政の垣根を越え、住民の方や民間の方とともに進める場面が多くありますが、ここ最近の私は、悩むことが増えていました。「行政の立場で何ができるのか」「あるべき姿は」。そんなことを頭の片隅で考えながら、日々の業務にあたっている部分がありました。そんなモヤモヤも抱えながら、神山研修を迎えました。
視察・交流での出会いと発見
企業との協働とは何か?-サテライトオフィスで感じた空気感

株式会社えんがわの本社であり、株式会社プラットイーズ、プラットワークスのサテライトオフィスの「えんがわオフィス」や、モノサスのサテライトオフィスを訪問。そこで見たのは肩ひじ張らず、町の生活に溶け込み働く、企業人の姿でした。企業側が「入ってきたかったから入った」という素朴さを感じました。外から“地方創生”を掲げて入るのではなく、暮らしの延長として根づいていく。そんな空気感を感じました。
「町のリビング」で見た日常──大埜地の集合住宅と鮎喰川コモン

町産材で建てられた集合住宅と、そのそばに開かれた“町のリビング”鮎喰川コモンでは、学校帰りに集まり川辺で遊ぶ子どもたちや、コモンで本を読んだり地域の人と話す姿が当たり前のようにありました。自然と遊びが共にある風景に、どこか懐かしさを覚えました。
食から学ぶ公教育と地産地食──フードハブプロジェクト

まちの食農教育の樋口さんから、食農教育について伺いました。「食べる」について五感を通して学ぶ、その体験を公教育で作っていく想いと熱量に触れました。十勝と神山で前提は異なっても、「食が暮らしと切り離されている」という部分は共通していると感じました。ランチではフードハブが運営する食堂「かま屋」で地産地食を体験しました。
アーティスト・イン・レジデンスがつくる土台

山中に点在する作品群をめぐりながら、この取り組みが長年にわたり地域の「わたしたち」の手によって続けられてきたことの重みを体感しました。継続の蓄積が町の寛容さを生み、挑戦の裾野を広げること、アーティスト・イン・レジデンスをはじめとする数々の実践がミルフィーユのように折り重なり、現在の神山を形づくっていることを学びました。
「いいゆるさ」に出会う——予定表にない学び

川で獲ったモクズガニのプレゼント、つなぐ公社・馬場さんとの交流会、道すがら出会った元神山塾生による阿波踊りの即席レクチャー……。数え切れないスケジュール外の出来事から、神山町の「いいゆるさ」を実感しました。五感で受け取った経験から机上では得られない気づきを与えられ、自分のあり方を問い直させてくれました。
爆速の神山町研修を終えて——「みんな」ではなく「わたしたち」

神山の取り組みには、遊びの延長にある実践が多いと感じました。アーティスト・イン・レジデンスも「こんなことしたい」という気持ちに「やったらええんちゃうん」というゆるい連鎖が起きる。そこには、大きな視点を持ちながらも、同時に身近な暮らしを楽しむ姿勢が息づいていました。私が強く感じたのは、それらが「みんなやだれかのため」ではなく、「わたしたち」のサイズではじまっていることです。
行政の立場にいると、「公平に」「広く」「みんなのために」というスケールで物事を考えます。もちろんそれは必要ですが、同時に「わたしたち」という範囲でものを考え、暮らしを動かすことに大きな意味があることを神山で実感しました。
これからの生活では「わたしたち」の視点を大切に、
大きな方向感を見失わずに、日常の範囲で試し、続けていきます。
リレイションと神山町の皆さま、研修期間中は大変お世話になりました!
おまけ―徳島・神山で出会った魚


関連記事
-
2017.02.15
-
2024.06.26
-
2024.09.25
-
2020.06.01
-
2017.05.15
-
2016.06.16