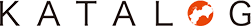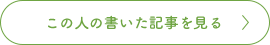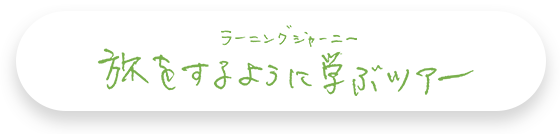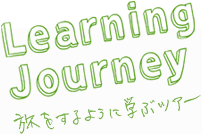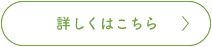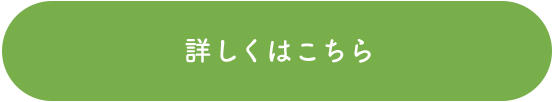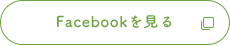こんにちは、上田です。
以前、KATALOGブログでも取り上げた「お茶摘み」。
ですが、今回お話しする「お茶摘み」は、みなさんがイメージするであろうものと一味違います。
一般的なお茶摘みは、あたたかくなった新緑の春の茶畑をイメージしますが、
私はここ3年ほど、キンと冷えた山奥でお茶摘みをしています。
冬本番の1月から2月末まで行う冬の茶摘み。
そのお茶の名は、寒茶。
春に摘むお茶と味は違うの?
寒い時期に摘んだらどうなるの?
どこで摘んでるの?
誰が摘んでるの?
などなど、寒茶についてご紹介していきたいと思います。
日本で一番早い茶摘み

寒茶の舞台は徳島県最南端の町、海陽町。
海陽町の中心部から車で約40分ほどの、携帯の電波も届かない山あいにある、
宍喰地区の久尾(くお)・船津(ふなつ)地域で主に寒茶が作られています。
私は3年前、久尾地域にお住いの石本アケミさんと出会いました。
石本さんこそが、宍喰寒茶生産組合を立ち上げた第一人者です。
宍喰寒茶生産組合は、約30年前に同町の農家が集まってつくられ、
寒茶摘みから出荷までを手掛けている組合です。
昔から宍喰地区では、春に摘む柔らかい茶葉よりも甘くておいしいということで、
冬にお茶を摘んで飲んでいるそうです。
もともと石本さんのお宅の裏庭にもお茶の木があり、
どうにかこのお茶をいかしていきたいという思いで活動を始めたそうです。
寒茶はカフェインやタンニンが非常に少なく、苦みや渋みがあまりないのが特徴。
確かにまろやかで甘みがあります。
石本さんは普段寒茶しか飲まないそうで、
他のお茶との違いはよくわからないと言っていましたが(笑)。
刺激が少なく胃に優しいので、子どもからお年寄りまで安心して飲めます。
地元の方によると、お湯で煮出すより水出しのほうが、
さらに甘みが増しておいしいと教えてもらいました。
私も飲ませてもらいましたが、より渋みが減って甘みが際立っている気がしました。
寒さの中で

「年末は寒茶の準備でゆっくりできなかった」と言う石本さん。
今年も年明けから寒茶摘みがはじまりました。
私は1月半ば、寒茶摘みをさせてもらいに行きました。
午前中は石本さんのお宅の裏山の急斜面にある茶畑で作業しますが、
日の傾きに合わせて、午後からは家から見下ろした先の川の近くの茶畑に移動します。
日が当たらないところは、寒くて作業ができないからです。
晴れた日でも、日がかげるのが早く、
厚着をして手袋をはめていても1時間もすれば手の感覚がなくなります。

寒茶は、寒くならないとうまみや甘みが出ないし、
寒すぎても霜でやけて赤くなってうまみがなくなるので、
寒さがピークのこの限られた時期に集中して収穫する必要があります。
気休め程度に手をもんで温め、寒さに少しくじけそうにもなりますが、
肉厚で硬く引き締まった葉っぱをちぎる「ぷちっ」という音は、
なんともいえない心地よさがあります。
石本さんは、
「ぷちっという音がたまらない。何の音もなくひたすら摘んでいられる」
と笑顔で話してくれました。
私には、農作業するときはラジオをききながら黙々と行うという勝手なイメージがありますが、
石本さんは川のせせらぎと鳥の鳴き声と、
あとは寒茶の「ぷちっ」「ぷちっ」というかわいらしい音の中で作業します。
寒さに手がかじかんでも、時間が限られていても、
たとえ急こう配でしんどくても、石本さんは冬にお茶を摘みます。
頭上を飛び交うトンビがフンを落としても、そこをさけて綺麗な葉をひたすら選別し、
かずらの蔓が絡まったり雑草が生えてきても、農薬を使わず夏場にきちんと刈り取って、
冬にお茶を摘みます。
石本さんのその姿勢から、人間の作業しやすい環境を作るのではなく、
自然に沿った暮らしを当たり前のように営むという印象をうけました。
寒茶ができるまで


お茶の葉を摘んでからも一苦労です。
まず収穫した葉の掃除をして、窯で30分ほど蒸します。
蒸した茶葉を機械で荒もみしたあと、手で細かくもみこみます。
その後一晩寝かせ、4日間くらいハウス干し。
最後は1日天日干しをして完成です。
なにを、どう残していくか

お茶摘みもそうですが、干す作業では作業の進行が天候にも左右されるので、
なかなか予定通りいかない時もあります。
葉を摘むのはいいけれど加工が大変だ、という方もいて、
久尾地区で組合に入って作業に従事している人は石本さんを含め現在3名ほど。
実際に、私も加工の一部を見せてもらったことがあるだけで、
実際におこなったことがあるのは茶摘みだけです。
毎年地元の小学生が授業の一環で茶摘みに来たり、
寒茶に興味のある方や石本さんのお知り合いの方も茶摘みのお手伝いをしていますが、
茶摘み、加工、パッケージング、販売、イベント出店などのすべてを一貫して行っているのは石本さんだけです。
寒茶は各種メディアで取り上げられていることもあって、全国的に人気です。
近隣の町のお店に出荷したり、地元のホテルに定期的に届けたりもしていますし、
石本さんへ向けて「どうにか作り続けてほしい!」と言った町内外の声が後を絶ちません。
そのたびに石本さんは、「来年できるかわからない」といいます。
寒茶が終われば3月から稲の準備に入り、4月には田植え、5月は春のお茶、夏には草刈り、
その間畑仕事やみそづくり。
また、加工業の講習に行ったりイベントの出店をしたりと活動的な石本さんは、今年80歳です。
石本さんのお孫さんが「ばあちゃんの仕事に興味がある」と言ってくれたそうですが、
石本さん自身、嬉しい反面、こんなしんどくて大変な仕事(生活)をお孫さんがしていくと考えると複雑な気分だ、と言っていました。
全国的に少子高齢化が進み、過疎地域が増え、消えていってしまう集落も少なくありません。
同時に、なにを残していくか、どう残していくのかが問われてもいるような気がします。
かけがえのない文化や暮らし、美しい景色を、いかに未来に残していくか。
変わらないためには、どうやって変わり続けていけばいいのか。
そんなことを考えながら、石本さんが作った寒茶を飲み、
また来年も石本さんと一緒におしゃべりしながら冬の茶摘みがしたいなと思いました。
《こちらの記事もどうぞ》
こちらは新緑の季節のお茶摘み。大川村での茶摘みと製茶の様子。
五感で感じるお茶づくり
寒茶だけじゃない、海陽町の魅力。
海・山・川。懐かしいまち、海陽町
関連記事
-
2016.06.30
-
2020.02.12
-
2021.04.26
-
2022.04.14
【レポート】越智清仁さん 就職氷河期世代活躍支援セミナー 「社員の個性を生かした職場づくり −働き方の多様性に対応した新しい人材採用・育成のあり方−」
-
2022.12.12
-
2016.12.08