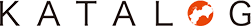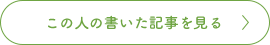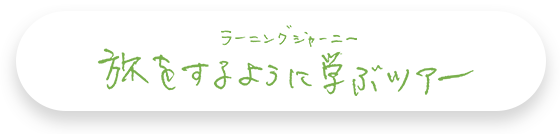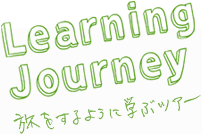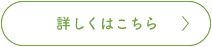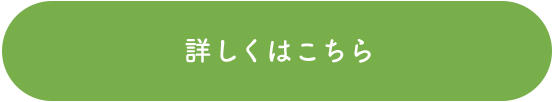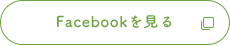“教室の外に広がる、問いと発見の一日”
8月9日、徳島県立川島高校の生徒さん14名と乾教頭先生、山﨑先生が、探求学習の一環で神山町を訪れてくれました。コーディネートを担当した私にとっても、まるで一緒に旅をしているような一日でした。
町ぐるみの探求学習
神山は、大人たちが日々 “探求学習” をしている町です。仕事も暮らしも、試行錯誤と挑戦の積み重ね。その空気を、生徒さんたちに少しでも感じてもらいたい — そんな思いでご案内が始まりました。
自己紹介は「自分の好きなもの」から。
音楽、ダンス、アニメ、鉄道、テニス、卓球…表情は緊張が感じられるような少し固い感じですが、笑顔も垣間見え「ああ、この瞬間からもう探求は始まっているな」と思いました。
アートが問いをくれる
まず向かったのは「創造の森」。木立の間に、神山アーティスト・イン・レジデンスの世界各国のアーティストが残した作品が点在しています。
2018年の Karin van der Molen さんの作品「神山金継ぎ」を見つけた瞬間、「これ教科書に載ってる!」と声があがりました。想像よりずっと大きな実物に、目を丸くして見入る姿。触れて、歩き回って、写真でしか知らなかったアートが、全身で感じる存在に変わっていくのが分かりました。
弊社代表祁答院からは「起こった事実はひとつ。でも、どこから見るかで意味は変わる。できない理由より、できる方法を考えてみよう。」との話。アートは正解を与えないけれど、視点を変えるきっかけをくれる — そんな学びが森の中にありました。
生徒さんの感想も印象的でした。
「自然とアートが調和している」
「景色によって見え方が変わる」
「本でしか見たことがなかったけれど、実物に出会えてよかった」
歩みを進めるごとに、世界が少しずつ広がっていくようでした。
町の暮らしと人に出会う
お昼は「かまパン&ストア」で買ったパンを持って、WEEK神山へ。すだちスカッシュやうめスカッシュを片手に、笑い声が絶えない昼食になりました。
ここには川島高校の阿部校長先生も駆けつけてくださり、アイスクリームの差し入れをしていただきました。皆さん、暑い中たくさん歩いたので冷たくて甘いプレゼントにほっこりしました。ありがとうございました!!
食後は祁答院による神山レクチャー。「なぜ高校に通っているのか?」「探求とはなに?」という問いかけから始まり、神山がどう変化してきたか、そして五感を磨くことの大切さについて話しました。旅や読書、人との出会い — それらが気づきや発見、教養につながっていく。生徒さんたちも真剣に耳を傾けていました。
午後はフィールドワークへ。
寄井商店街を案内いただいた “ハムさん” こと吉沢公輔さんに質問!「横浜より徳島のいいところは?」ハムさんは、ズバリ「不便だから面白い」という言葉。不便さが暮らしを考えるきっかけになり、挑戦の余地を与えてくれることを教えてくれました。
ゲストハウス「On y va」の斎藤郁子さんに質問!「神山の魅力ってなんですか?」郁子さんは、ズバリ「コミュニティの強さ」というシンプルで力強い答え。コミュニティにはさまざまな価値観や生き方が集まる。その多様さに触れることで、自分の視野も広がり、新しい問いが生まれると教えてくれました。
最後はまちのリビング「鮎喰川コモン」や KAMIYAMA BEER へ。朝から夕方まで、大自然の中、五感をフル稼働させたフィールドワークを終え、生徒さんからは「いろんな視点を持てて良かった」「誰に出会うかが大切だと分かった」という声が。中には「ビールが飲みたかった」というおもしろい感想もあり、思わず笑ってしまいました。
未来へ続く学びのタネ
この日改めて思ったのは、探求学習は授業や特別なイベントの時だけに、行うものではないということです。「日常の中にも探求のきっかけはある」と感じました。
教室や課題の中だけで行う探求も大切ですが、町を歩き、人に出会い、思いがけない景色や出来事に触れることで生まれる探求は、より濃く、より自分ごとになります。
生徒さんたちは、創造の森でアートに出会った瞬間に教科書のページと現実をつなぎ、寄井商店街では町の人の言葉から暮らし方の価値観に触れました。そうやって、「知識」と「体験」が繋がるたびに、目が輝き、言葉が増えていくのが分かりました。
神山の大人たちが日々探求を続けているのは、「問い」を持ち続けているから。問いは答えを探すためだけのものではなく、日常を新鮮に映すレンズでもあります。
この日生徒さんが持ち帰った問いは、もしかすると明確な答えが出ないまま育っていくかもしれません。それでも、その問いが人生のどこかで道しるべになる瞬間がきっと訪れるはずです。
そして私自身も、このフィールドワークを通して改めて思いました。探求は一方通行の教える・教わるではなく、出会った人同士のやり取りの中で自然に生まれてくるものだということ。生徒さんの素直な感想や驚きが新しい問いを生み、その場にいる全員の学びへとつながっていくものだと感じました。
生徒さんたちの笑い声や「面白い!」という素直な反応を見て、探求の入り口は難しい問いではなく、“楽しい”や“驚き”といった感情なのだということにも気づきました。心が動いたときに、もっと知りたい、考えたいというエネルギーが自然と湧いてくるのだと思います。
ふと見上げた山の景色、町の人との何気ない会話、道端のアート — そんな小さな出来事の中にも、学びのタネは隠れています。
その種に気づき、「面白そう」と手に取って、自分なりに育てていく。その積み重ねが、この町らしさであり、今回のフィールドワークを通して生徒さんたちに渡せた何よりの宝物だったのではないでしょうか。
この記事を書いた人

中岡 直子
徳島生まれ徳島育ち。神山塾16期を経てRELATIONスタッフに。 銀行勤務が長く、前職は製薬会社でMR。 3人の母でそろそろ子育てから解放予定!!今までは誰かのために生きてきたけれど、これからは自分を大切に、大好きな人達と居心地のいい場所で、毎日ご機嫌に過ごしていきたいと思う今日この頃…。アシスタントとして代表を支えられるように日々頑張っています。
関連記事
-
2021.08.05
-
2024.05.09
-
2023.03.27
-
2020.09.15
-
2020.11.10
-
2023.11.13