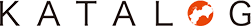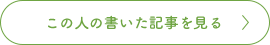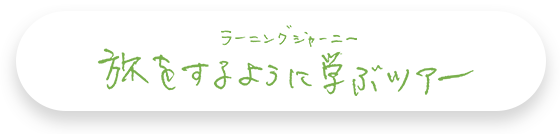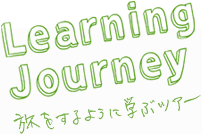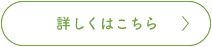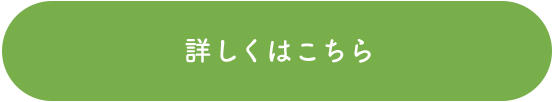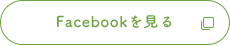皆さん、こんにちは。
プランナーの前田です。
最近、鼻がむず痒く、くしゃみが出始めました……。
これも春の訪れと、ポジティブに捉えるようにしています(笑)。
春を迎えるということで、この機会に私も新たなことをしてみようと思い、
今回は「徳島MONO×LOG」と題して、お気に入りの「もの」を紹介したいと思います。
「もの」は「語る」
はじめに、なぜこのKATALOG WEBで「もの」を語るのか。
私は前職で、ものづくり(眼鏡や、ネクタイなどの紳士服飾)に携わっていました。
もちろん現在は地域マネジメントを仕事としているわけですが、
そんな職歴を持つ私だからこそ伝えたいことがあります。
豊かな「もの」とは。
伝統や背景を感じる「もの」、人の手の温もりを感じる「もの」。
それらは、ただ単に「もの」ではなく、
ときに人と人との想いを繋ぐバトンのようなものではないかと思うときがあります。
そこには作り手のどのような思いがあり、どのような姿勢で作られているのかを知りたい。
そして、それを届けたい。
その「もの」の後ろ側にある人の想いを、
「MONO×LOG」として綴っていきたいと思っています。

今回取り上げるのは、この包丁。
これは、私が使っている大久保鍛冶屋の三徳包丁です。
私の周りの皆が
「優さん、大久保鍛冶屋の包丁を一度使ったらもう普通の包丁には戻れないよ」
と言うように、その切れ味は素晴らしく、
また、8割の切れ味からなかなか落ちません。
この包丁はどんな人が、どんな思いで作っているのでしょう。
では、取材当日の様子をお伝えします。
大久保鍛冶屋の工房を訪ねて

大久保鍛冶屋は、徳島県の勝浦町に工房を構えています。
徳島市の中心地から工房までは、車で1時間ほどの距離です。
勝浦町を横切る県道16号線を西に進み、小学校付近の小道に入ると
右手に小さな直売所が見えてきます。
その奥が、大久保鍛冶屋の工房です。
軽バンの横をするすると通り「こんにちは!」と声をかけると、
奥様が工房へ案内してくれました。

刃物作りの作業場を通ると、奥には炉のある部屋があります。
そこで農具(鍬)を作っている最中でした。
私「こんにちは、昨日お電話をさせていただいた前田と申します。
会社で『KATALOG』という地域広報媒体に携わっていまして……」
なぜかこのとき、ふと「職人気質」という言葉が頭に浮かび、やや緊張気味の私(笑)。
私「自身も学生の頃からものづくりに関心があり、
福井県の鯖江にある眼鏡の会社で働いていました。
“スローライフ”など、今地域での豊かな暮らしが取り上げられていますが、
僕は豊かな『もの』をテーマに発信したいと思っているんです!」

「そうか」と作業の手を止め、話していただいたのは、
大久保鍛冶屋 三代目の大久保喜正さん。
まずは刃物(包丁)に関する現状を話してくれました。
喜正さん「最近の包丁は、きちんとしたものがない。
ホームセンターに出回っているものなんかまさにそうや。
儲けだけを追求していては、まともな道具はできんわな。
使う人も道具に対する意識が低くなってしまった」
最近は物を買うにしても、ネットでの情報や評価を基準にして買うことが多くなってきています。
使う本人が自分の感覚でそのものを価値を見定める力が低くなることで、
製品のクオリティも下がるということは、確かにあるように思います。
私「大久保鍛冶屋さんの製品は、僕の周りでもとても評判です。
使っている印象としては、切れ味が落ちにくいというか、
8割の切れ味が長く続くというか……」
「それは、うちの製品の特徴を言い当ててるね! そうなるように作っているから」
作業場の奥からの声は、大久保鍛冶屋 四代目の大久保竜一さん。

竜一さんからは、その後刃物の硬度・切れ味の関係や、
刃物ごとの特性などを教えていただきました。
竜一さん「僕には兄弟がいて、 LEDで有名なある会社で働いている。
本当に両極端だよね。
彼は彼の働き方や暮らし方があり、僕には僕の働き方や暮らし方がある。
どちらがいいということではなくてね(笑)」
そう笑顔で話してくれる竜一さん。
ただやはり自分の仕事に話が及ぶと、職人としての目に変わります。
大久保さんの仕事観

私にいろいろと教えてくださる間も、喜正さんの手が止まることはありません。
この日は整形・焼きなましの工程を行なっており、
私も使っている包丁を作る様子を見せていただきました。
私「私も、ものづくりにとても興味がありますし、作業を見ていて楽しいです」
喜正さん「包丁のイメージって平たいだろ、二次元的というか。
でも平面を作っとる感覚とはちゃうな。
頭の中では1つ1つどこを叩いたらパランスの良いものになるか、
三次元的・立体的に考えとる」
「そうか、楽しいか。
でも作っとる方としてはこれはお金みたいなもんやから、生活をしていくためのな。
だから、間違ったことはできないという責任がある。
利益の追求だけを考えるといいものはできない。
いいものっていうのは、きちんと手間をかけたもんや。
手間をかけたら、利益は出ない。
でも手間をかけたら、いいもんができる。そこんとこが……な(笑)」
そう私に笑顔を見せて話してくれる喜正さん。
このころには私の緊張も幾分かほぐれてきました。
次にKATALOGのテーマでもある「受け継ぐ」「伝える」について。
私「私以外にもよく取材に来ると思うのですが、
このような伝統・文化を守ることは、大久保さんにとってどんな意味があるんでしょうか」
喜正さん「よく『伝統を守る』とか、特別なことのように言われとるが、
ワシらは昔からしていることをしているだけ。
だから、逆に間違ったことはできないわな」


喜正さん「昔からしていることと言っても、昨日と同じではダメ。
それではレベルが落ちるからな。
どうやったらええもんができるか、どうやったら昨日より使いやすいもんかできるか。
つまり『職人』っていうのは仕事への気質の問題やと思ってる。
それはIT関係でもシェフでも同じで、ワシはたまたま鍛冶屋やっただけ。
どんな仕事でも、もっともっと、奥へ奥へを追求していけばなんぼでも先はある。
大切なんは、これをやめないことやな」
「結局、変な時代に抵抗しとるんよ。
パンク精神というか、ロック精神というかな(笑)。
ワシらのやっとることは、それこそ太平洋に目薬を差しとる程度かもしれん。
けど、それでも正しいことをやっていきたい」
徳島県が認定する「阿波の名工」にも選ばれた喜正さんから発せられた言葉は、
意外にもとても柔軟で、かつ本当に基本的なことでした。
私の使っている包丁から聞こえた言葉のようなものは、
手間を惜しまず、工程を省かず、確かな技術によって作られた、
「堅実さ」なのかもしれません。
作り手から使い手へのバトン
工房を見学させていただいた後、喜正さんと竜一さんに直売所の中を見せてもらいました。
大久保鍛冶屋は、包丁や農具、山林刃物など、生活に密着した刃物を主とする「野鍛治」。
直売所には馴染みのあるものから、初めてみるものまで多種多様な刃物が揃っています。

私が不思議に思ったのが上の写真にある刃物。
一見3つとも同じもののように見えますが、それぞれに用途が異なります。
竜一さんに伺ったところ、
左から「鰻裂き包丁(左利き用)」「万能削り」「接木刃物」だとのこと。
鰻裂き包丁だけみても、写真一番左の「大阪型」と、
写真にはありませんが、東で使われる三徳包丁の先が鋭角になったような「江戸裂き」など、
使われる地域によって形状も異なるようで、東と西の文化(調理法)の違いなどがうかがえます。

上の写真は職人さん用の剪定鋏。
原理は片刃と片刃が合わさったものですが、
鋏作りは他の刃物と比べても難しいそうです。
竜一さん「量販店などでよく売っている剪定鋏は
刃と刃がピッタリ合わさっているでしょ。
あれは面と面で押し潰して切っているような感じ。
これは刃と刃の間に意図的に隙間を作っていて、
植木職人さんの加減で『点』で切れるようにしている」
「使い手のスキルか落ちると、道具も落ちる」と前述しましたが、
言い換えると、このような作り手の技術と配慮が、職人を技を支えているのだと感じました。
最後に − 生産者の思いが見える「もの」−
最近スーパーなどで「生産者の顔が見える野菜」というのがあります。
産地がわかるのに加え、生産者の顔が見えることで、
より安心しておいしく野菜がいただけるということなのでしょう。
でも、生産者の顔が見える「もの」って少ない気がします。
今回の私のブログでは、作り手である喜正さん・竜一さんの「声」を、
できるだけそのまま切り取ることを意識しました。
(走り書きでメモをとったため、方言などに誤りがあるかもしれませんが)
よくある謳い文句(製品の特徴)ではない、言葉の温度感、人間のあたたかさ、熱意……。
このような背景を知ると、包丁を使って肉や野菜を切る行為も、
今までとは異なった気持ちになるように思います。
よい「もの」は、使う人の「時間」を豊かにしてくれる。
私の発信こそ「太平洋に目薬」ではないですが、本当に些細なことです。
でも、よい「もの」がもたらす豊かな時間を、
作り手を含め、少しでも多くの人と共有できたら……。
今回はそのような想いで書いてみました。
最後に、取材をさせていただいた大久保喜正さん・竜一さん。
ご協力いただき本当にありがとうございました。
【大久保鍛冶屋 ホームページ】
http://www.shokokai.or.jp/100/36/3630110026/index.htm
【大久保鍛冶屋 Facebook】
https://www.facebook.com/okubokajiya/
《こちらの記事もどうぞ》
徳島の伝統的なものづくり「藍染め」を紹介した記事。
徳島の藍の魅力を体感する〜本藍染ワークショップレポート〜
この記事を書いた人

前田 優
地域マネジメント事業のプランニング・ディレクションを担当。2019年から熊本県南小国町で「地域人材マネジメント×温泉旅館」のプロジェクトにチャレンジ。民藝品や伝統工芸品が好きで、最近のマイブームは酒器。お刺身をアテにお気に入りの酒器で日本酒を呑むのが何よりも幸せ。
関連記事
-
2020.01.08
-
2021.05.19
-
2021.12.28
-
2023.10.30
-
2019.09.20
-
2017.07.26